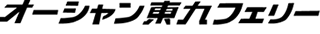中国輸出規制の動向とその影響、日本企業のリスク対策を解説!

中国は近年、2023年より半導体などに使われる原材料などの事実上の輸出規制を強化し続けており、世界的な影響をもたらしています。日本にもその影響が及んでおり、リスク対策が求められています。
今回は、中国輸出規制の基本から目的、最新動向、世界への影響、日本企業のリスクと現状、リスク対応の方法を解説します。

コスト削減・リードタイム短縮を実現
中国輸送サービスのご案内
中国輸出規制とは?その目的を解説
まずは中国輸出規制の概要から目的などを見ていきましょう。
中国の輸出規制とは?
中国における輸出規制とは、中国から他国への貨物や技術の輸出を規制することを指します。
中国の輸出規制は、大きく2つの関連法に基づいています。
1.対外貿易法などに基づくもの
一般的な輸出管理です。環境保全、国際条約の履行、国内の供給不足への対応など、海外諸国との貿易秩序を維持する目的で規制が行われます。国内の供給不足のため、国内の天然資源を保護するため、輸出先国の市場容量が有限であるなどに基づいて規制が行われます。
2.輸出管理法などに基づくもの
国家の安全保障などに関わる輸出管理です。規制の対象となるのは、両用品目を中心に、軍用品や核関連などの貨物や技術が対象です。両用品とは、民生用と軍事用の両方の用途を持つもの、もしくは、軍事的潜在力の向上に資するものを指します。
輸出管理法が2020年に施行
輸出規制については、2020年に施行された輸出管理法が重要なトピックスとなっています。
従来より、両用品目や軍用品、核などは輸出管理規制がありましたが、体系的ではないとの観点から不十分と考えられていました。安全保障貿易管理の観点から、それらの輸出を包括的・全体的に管理し、規制強化するべく、制定に至りました。
また、後ほど詳しく解説しますが、2024年6月には「レアアース管理条例」が発表され、2024年10月1日より施行されています。スマートフォンやEV(電気自動車)、ミサイルなどに使用するレアアース(希土類)の輸出入を含めた管理について明確に定められました。輸出規制においては、対外貿易法や輸出管理法などの枠組みが前提となっています。
中国輸出規制の最新の動向
中国輸出規制の最新の動向を見ていきましょう。
近年の動向
中国では、生産量において占有率の高い希少金属(レアメタル)や希少土類(レアアース)の輸出規制を2023年頃から強化し、2024年、2025年と相次いで発表しています。
2023年には2024年8月1日よりガリウムとゲルマニウムという2つのレアメタルの輸出制限を発表しました。
レアメタルは、先端産業に欠かせない半導体はもちろん、軍事技術にも重要な資源です。それらの輸出規制を強力に行うことは、国際市場に大きな影響をもたらします。
2024年6月には「レアアース管理条例」を発表しました。
JETROによれば、この条例では、「国内のレアアースの採掘、抽出・分離、金属精錬、総合的な利用、流通、輸出入などの活動に対して適用される」とし、「(1)レアアース資源保護の強化、(2)レアアースに対する管理体制の整備、(3)レアアース産業の質の高い発展に向けた取り組み、(4)レアアース産業チェーン全体の管理体系の整備、(5)管理措置と不法行為責任の明確化などについて具体的に定めている」といいます。
出典:JETRO「国務院がレアアース管理条例を発表、産業チェーン全体の管理強化(中国)」
これにより、本格的にレアアースの規制が強化されました。
また「両用品目輸出管理条例」が2024年12月1日から施行され、両用品目の輸出管理も強化されました。
【関連リンク】
中国輸出規制の近年のレアメタル・レアアース関連品目リスト:企業が知るべきリスクと対策
2024年末から2025年にかけての動向
2024年12月にはガリウム、ゲルマニウム、アンチモンなどについて対米輸出を原則禁止し、黒鉛の対米輸出の審査を厳格化しました。
2025年2月にはタングステン、モリブデンなどの5種類のレアメタルを、2025年4月には、サマリウム、ガドリニウム、テルビウムなどの7種類のレアアースを輸出規制の対象に追加しました。
中国輸出規制がもたらす世界への影響
近年のレアメタルを中心とした中国輸出規制は、世界へ次のような影響をもたらしています。
価格高騰
半導体の製造などに不可欠なレアアースの中国からの輸出が規制されることで、国際市場においては供給が間に合わず、価格が急騰しています。
輸入業者の在庫確保
中国からのレアアース輸入を担う業者の多くは、在庫確保のために先行して動くことがあり、より供給不足を深刻化させ、需要のひっ迫を招いています。
技術開発や製造の停滞
レアメタルの供給が減ることで、技術開発や製造面の進歩に制限がかかります。

コスト削減・リードタイム短縮を実現
中国輸送サービスのご案内
中国輸出規制による日本企業のリスクと現状
中国輸出規制を受け、日本企業はどのようなリスクがあるのでしょうか。すでにリスクへの対応策を講じた日本企業の例も出てきていますので、あわせて見ていきましょう。
原材料の供給不足による生産停止リスク
例えばEV製造に必要なレアメタルの供給不足が高まれば、生産停止に追い込まれます。実際に、レアメタルの供給難が影響し、国内の有名自動車メーカーが一部の国内生産を停止した例があります。今後も、さらに同様のケースが増える恐れがあります。
中国依存によるリスク
技術開発や製造面で中国資源に高い依存状態である場合、特に打撃は大きいものとなります。
国内の工業メーカーは建設機械用部品を中国に依存していたため、リスク回避のために調達を複線化した例があります。
中国輸出規制による日本企業のリスク対応の方法
日本企業のリスクは、次の方法で対応することが有効と考えられています。
ビジネスモデルやサプライチェーンの再編検討
中国資源への依存を脱するために、グローバルレベルでサプライチェーンにおいて中国に依存する物資を洗い出し、脆弱性を補強し、再編を検討する必要性が増しています。今後も長期的な輸出規制の影響を受ける見通しがあることから、一時的な対応ではなく、ビジネスモデルや事業戦略の見直しまで求められる状況となっています。
代替手段の検討・代替材料の開発
調達先の変更、複線化など調達における代替手段を検討するほか、レアメタルの代わりになる材料を開発することも一案です。
備蓄制度とリサイクル
日本政府は過去よりレアメタル等の備蓄制度を設けていましたが、今後はより一層強化を図る見通しです。また廃棄物に含まれるレアメタルなどのリサイクルは短期的に供給量を増やす手段として注目されています。
社内体制の整備
中国との貿易を行う企業は、常に変化する中国の輸出規制に関する最新情報を追いながら、企業が独自に持つ輸出管理の体制を強化し、柔軟に対応していく必要があるでしょう。
度重なる制度変化への対応には、専門家の知見を借りるのも一案です。
まとめ
中国の近年続くレアメタルやレアアースなどの輸出規制は、価格高騰、輸入業者の在庫確保による需要ひっ迫、技術開発の停滞などさまざまな世界的な影響をもたらしています。
日本にもその影響は及んでおり、すでに対応策が講じられています。日本企業のうち、中国から原材料調達の必要性がある場合には、リスクへの対応が急がれます。適切な対応を進めていきましょう。

コスト削減・リードタイム短縮を実現
中国輸送サービスのご案内